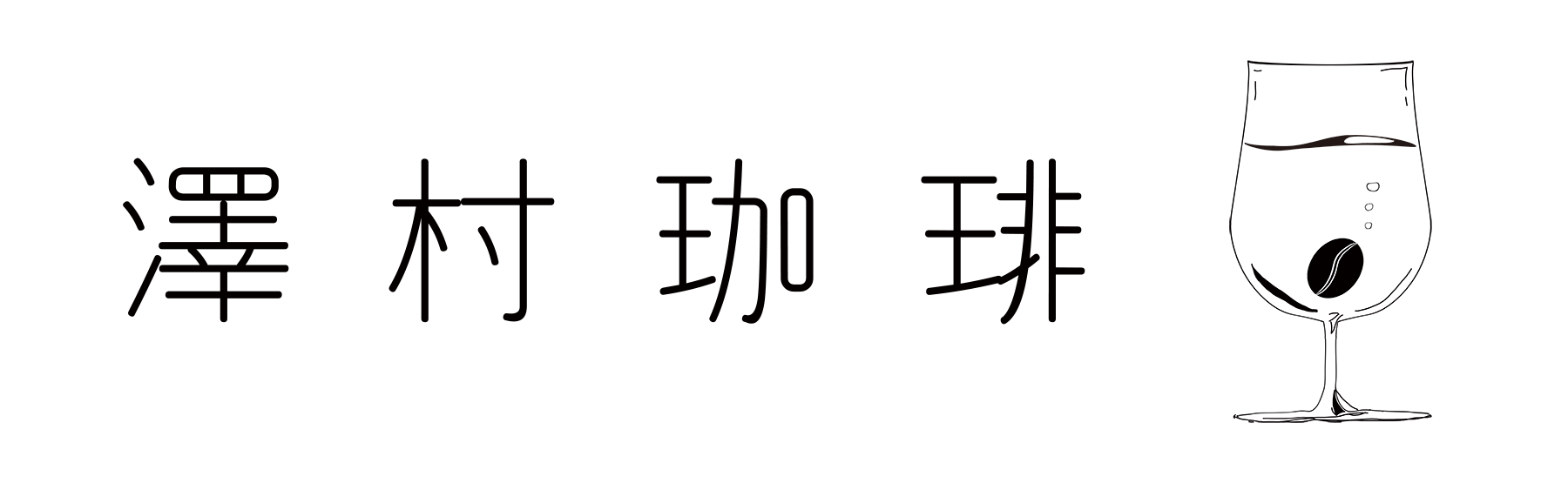大会レポート
COFFEE ROASTING COMPETITION
JAPAN to NEW ZEALAND 2025
2025年5月30日に行われたこの大会。
結果は準優勝でした。

今回はこの大会で何を意識したのか、書いていこうと思います。
まず、
この大会は優勝目指してましたので、シンプルに悔しいです。
さて、そんな感情は一旦置いておいて、振り返っていきましょう。
まずはレギュレーションの確認から。意識したところは…
1.オーディエンス票がある & ジャッジの方々がスラッピングするかわからなかったので、香りや酸がわかりやすい豆を選ぶ。
2.本線と予選で日にちが空くので、なるべく焼いてすぐの状態を提出する。
3.ナチュラル部門なので、ベリーのフレーバーだけに頼らないフレーバーで勝負する。
そして、選んだ豆は…
Tamru Ethiopia 2024COE16st 74158 Natural
そうです。とんでもなく美味しい豆で勝負しました。
明確なブルーベリーのフレーバーがあり、白い花のニュアンス、ピーチや柑橘類も感じられ、Natural でありながらすごくクリーン。はじけるような酸が特徴です。
なんだこんなん使うなら楽勝じゃん。と思われるかもしれません。
COEの10位代の豆は、かなり美味しいが、完全無欠ではありません。
何かしらが及ばぬが故の2桁順位なのです。
私はこの順位帯のCOE豆が好きで、
我々焙煎人が試されているように思います。

この豆の難しいところは、
1.ブルーベリーのフレーバーを出すためには、メイラード反応初期の段階で、熱伝導をうまく使う必要がある。
2.1を遂行すると焙煎時間がかなり短くなってしまう。
3.焙煎時間を伸ばすとフローラルが消えて、ベリーだけのフレーバーになる。
これらの解決策として、
「焙煎時間がすごく短くても、生焼けや未発達にならないように焼く」
この究極とも言える課題をクリアする必要がありました。そこで解決策として一つ…
「メイラード反応初期のドラムの回転数を下げるアプローチ」を取りました。
これにより、釜から豆への伝導熱を高めることに成功しました。
それ以外では、ストレッカー分解による酸の種類の増加や、段階的なカラメル化、過度なメイラード反応を起こさないことによる後味の綺麗さなど、この辺りはいつも意識しています。
結果、後味や質感で点を落とす人が数名いらっしゃったのです。これは…
後味が綺麗→後味が弱いのと捉える人がいた。
ということなのかなと。これを踏まえて、これからの課題は…
「今までのフレーバーや酸の強度を保ちながら、後味の強度を上げる」
簡単そうですが、すごい難しい…焙煎は沼です。
そう、これからの課題があるということは、
またこの豆で大会に臨むという事。
実は前哨戦だったこの大会、次はいい結果出したい。
いつもみなさんの応援、豆やドリンクの購入が
大会挑戦の力になってます。
本当にありがとうございます。
そしてこれからもよろしくお願いします。